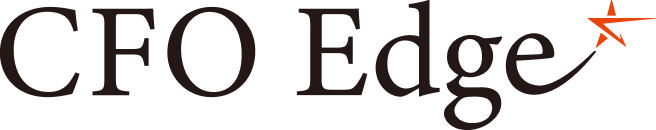はじめに
近年、企業の経営環境は急速に変化しています。労働力人口の減少、テクノロジーの進化、そして経営管理の高度化といった要因が複雑に絡み合い、経理・財務部門はこれまでにない課題に直面しています。
これらの課題に対応し、企業が持続的な成長を実現するためには、経理・財務部門における業務改革が不可欠です。本稿では、CFOの皆様に向けて、業務改革を成功させるための具体的なステップと方法論を解説します。
経理・財務部門を取り巻く環境変化と業務効率化の必要性
近年、経理・財務部門を取り巻く環境は大きく変化しており、企業は以下の課題に直面しています。
- 労働人口減少に伴う省力化
日本の労働生産性は先進国と比較して低い水準にあり、労働力人口の減少も深刻化しています 。経理・財務部門においても、人材の確保・育成は重要な経営課題であり、業務効率化やリモートワークへの対応、アウトソーシングなどを通じた省力化への取り組みが急務となっています。 - データに基づいた迅速かつ正確な情報提供
不確実性の高い経営環境において、経理・財務部門には、データに基づいた迅速かつ正確な情報提供が求められます。そのためには、テクノロジーを活用した業務効率化と、より高度な分析を可能にするための業務改革が不可欠です。 - テクノロジーを活用した業務効率化とビジネスモデルの変革
クラウド、ビッグデータ、AI、IoTなどのテクノロジーは、経理・財務部門の業務を大きく変革する可能性を秘めています 。これらのテクノロジーを積極的に活用し、業務効率化だけでなく、ビジネスモデルの変革に繋げていくことが重要です。
これらの変化に対応するため、経理・財務部門は業務効率化を加速させ、より高度で戦略的な業務にリソースを集中する必要があります。
経理・財務部門における業務改革のステップ
これらの課題を解決し、変化する経営環境に対応していくために、経理・財務部門は以下のステップで業務改革を進めていくことが効果的です。
I. 目的の明確化
業務改革に取り組むにあたって、最初に「何のために」業務を変革するのか、その目的を明確にし、関係者間で合意しておくことが重要です。目的が明確であれば、課題の優先順位付けや施策の意思決定を行う際に、立ち返るべき判断軸となります。
II. 現状把握
目的が明確になったら、次に現状の業務を詳細に把握します。経理・財務部門の業務を「見える化」するために、年間・月間業務スケジュールや業務フロー、業務一覧などの手法が有効です。これらの情報を整理することで、手作業が多い業務、特定の担当者に依存している業務、非効率な業務などを洗い出すことができます。

III. 改善策の策定
現状把握で洗い出した課題に対して、具体的な改善策を検討します。改善策を検討する際には、「ECRS」というフレームワークが有効です。
- Eliminate(排除): 業務自体をなくすことができないか検討します。
- Combine(統合): 他の業務と統合できないか検討します。
- Rearrange(再配置): 業務の順序を変更できないか検討します。
- Simplify(簡素化): 業務をもっと簡素化できないか検討します。
一般的に、排除の効果が最も大きく、簡素化の効果が最も限定的であるため、まずは業務自体をなくすことができないかという視点から検討することが重要です。
IV. 実行計画の立案
改善策が決まったら、具体的な実行計画を立てます。実行に必要なスケジュール、関係者、リソース、コストなどを明確にし、定量的な効果と定性的な効果を試算します。定量的な効果とは、「残業時間の削減」や「人件費の削減」など、数値で表せる効果のことです。一方、定性的な効果とは、「リモートワーク化」や「従業員満足度の向上」など、数値化が難しい効果のことです。
これらの効果を説明することで、経営層からの承認を得やすくなります。
業務効率化を実現するための具体的な改善策
経理・財務部門の業務効率化を実現するための具体的な改善策としては、ECRSの観点から考えると、以下のようなものが挙げられます。
I. 作成資料の見直し
現在作成している資料が本当に必要なものなのか、改めて検討します。システムの進化によって、過去には必要だった資料が不要になっているケースも少なくありません。
II. 業務の自動化
業務自動化ツールを活用し、データの取得や加工などの定型業務を自動化します。自動化ツールは、以下の4つの条件に当てはまる業務に特に有効です。
- 単純性: 経験や判断を必要としない、単純な業務であること。
- 定型性: 一定のルールに従って処理できる、定型的な業務であること。
- 反復性: 毎日、または定期的に繰り返される業務であること。
- 連続性: ある程度まとまった量の業務であること。
III. データの入手方法の見直し
経理・財務部門で加工するデータの収集方法に改善の余地がないか検討します。データのレイアウトやフォーマットを統一化したり、必要な情報を他部署から提供してもらったりすることで、業務効率化に繋げることができます。
IV. シェアード化・アウトソーシング
業務を特定の部署や会社に集約することで、効率化を図ります 。シェアード化やアウトソーシングを実現するポイントとしては、同種の業務におけるルールや業務手順の統一化です。シェアード化には、以下のようなパターンがあります。
- 本社の経理・財務部門にグループ会社の経理を集中
- シェアードサービス子会社にグループ会社の経理を集中
- グループ外のアウトソース会社にグループ会社の経理を集中

さいごに
経理・財務部門における業務改革は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。本稿で解説したステップと方法論を参考に、CFOがリーダーシップを発揮し、自社の状況に合わせて業務改革を推進することで、企業価値の向上に繋げてください。
変化の激しい時代において、経理・財務部門が企業の成長を力強く支える存在となるために、CFOの皆様のリーダーシップに期待しています。