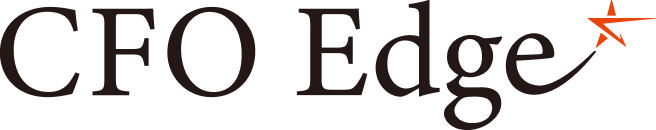はじめに:「資本コスト経営」の裏で、静かに迫る会計基準の大きな変更
金融庁や東京証券取引所からPBR(株価純資産倍率)改善など「資本コストや株価を意識した経営」の実現が強く要請される昨今、多くのCFOがその対応に注力されていることでしょう。しかしその裏で、自社の企業価値の前提を揺るがしかねない「リース会計に関する会計基準(以下、リース新基準)」の適用が、2027年4月1日以後に開始する事業年度から目前に迫っています。
この新基準の核心は、これまで多くの企業で費用処理(オフバランス)されてきたオペレーティング・リースが、原則としてすべて資産・負債として貸借対照表(BS)に計上されることにあります。これは、財務諸表の構造そのものを大きく変えるインパクトを持ちます。
本稿では、この変更が単なる会計処理の変更に留まらず、CFOが主導する経営戦略や財務戦略にいかなる影響を及ぼすのか、そしてこの変化を企業価値向上に繋げるために今から何をすべきか、その戦略的論点を解説します。
なぜ「たかがリース」ではないのか? CFOが直視すべき3つの経営インパクト
リース新基準の影響は、経理部門だけで完結する問題ではありません。
CFOが直接関与し、経営マターとして捉えるべき、3つの大きなインパクトが存在します。
インパクト①:経営指標の変動とステークホルダーへの説明責任
新基準の適用は、貴社が対外的に公表している重要経営指標(KPI)を直接的に変動させます。
貸借対照表(BS)への影響
これまでBSに計上されていなかったオペレーティング・リースについて、「使用権資産」が資産の部に、「リース負債」が負債の部にそれぞれ計上されます。これにより総資産と総負債が同時に増加し、結果として自己資本比率は低下する傾向にあります。
損益計算書(PL)への影響
従来、支払額に応じて費用計上されていたリース料は、「使用権資産の減価償却費」と「リース負債に係る利息費用」に分解されます。減価償却費は営業費用ですが、支払利息は営業外費用として扱われるため、結果として営業利益やEBITDA(利息、税金、減価償却費控除前利益)は増加する傾向にあります。
経営指標への影響
上記の変更により、ROA(総資産利益率)は、分母である総資産の増加影響が大きく、低下する傾向にあります。これらの会計指標の変動は、現在の中期経営計画で目標として掲げているKPIの前提を覆し、投資家や金融機関といったステークホルダーへの丁寧な説明が不可避となることを意味します。
インパクト②:財務戦略への直接的影響
財務指標の変動は、CFOが管掌する財務戦略そのものにも影響を及ぼします。
財務制限条項(コベナンツ)
負債の増加は、金融機関との借入契約に定められた財務制限条項に抵触するリスクをはらみます。事実、同様の基準(IFRS16号)を先行導入した海外企業では、自己資本比率への影響から契約の修正が必要となった事例も報告されています。
M&A・企業結合
M&Aの局面では、リースは原則として企業結合日時点での時価評価の対象となります。市場価格に比べて有利または不利なリース契約については、その差額がのれんや負ののれんに影響を与える可能性があり、企業価値評価における新たな論点となります。
インパクト③:想定外の契約も対象に?リース取引の範囲拡大
新基準は、契約書の名称ではなく、その「実質」でリース取引を判断します。
契約書に「リース」と書かれていなくても、「資産が特定されているか」「その資産から生じる経済的便益のほとんどすべてを享受できるか」「その資産の使用を指図できる権利を有しているか」といった要件を満たす場合、リースとして会計処理する必要があります。これにより、これまで費用として処理していた「サービス契約」や「業務委託契約」などもリースの対象となる可能性があります。
全社的な契約を洗い出す過程で、これまで管理が不十分だった契約や、潜在的なリスクが可視化されることは、ガバナンス上の大きな気付きとなるでしょう。
IFRS先行企業が直面した「3つの壁」
幸いにも、私たちには同様の基準であるIFRS16号という先行事例があります。多くの企業が経験したプロジェクト上の苦労から得られる教訓は、これから対応を進める日本企業にとって貴重な指針となります。特に、CFOや経営層の関与度合いが、プロジェクトの円滑な進行を左右する場面も見られました。先行事例から学ぶべきポイントは、決して他人事ではありません。
壁①:「これは単なる会計ルールの変更だ」という過小評価
最も多く見られたのが、「リースがBSに計上されるだけだろう」という、影響の過小評価です。しかし、実際には、リース期間の算定や実質リースの判定といった、経営者の意図や事業実態を反映する「会計上の高度な判断」の連続であり、当初の想定を大幅に超える資産計上が必要になった事例が多数発生しています。
その結果、プロジェクトの終盤になって初めて、Excel管理の限界とシステム対応の必要性が発覚。IT部門へ短期間での対応を要求することになり、リソース確保に難航したり、現場が疲弊したりする事態を招いたのです。
壁②:「これは重要性の低い取引だ」という安易なスコープアウト
次に陥りがちなのが、CFOの関与がないまま、「影響は軽微だろう」という目の前のPL計上額だけで判断を進めてしまうケースです。月々の支払額の大小といった表面的な情報のみで、安易に子会社や特定の契約を検討対象から除外してしまいます。
しかし、その後、実質リースの洗い出しやリース期間の再検討が進む中で、それらが無視できないインパクトを持つことが判明。慌てて追加調査に走るという、プロジェクトの迷走を招く大きな手戻りが発生しました。また、既存のリース台帳のデータを信頼していたものの、いざ精査を始めると情報が不正確・不十分であることが発覚し、契約書との照合という膨大なデータクレンジング作業に「半年以上を費やした」という事例も決して稀ではありません。
壁③:適用時点の数値算定に注力し、適用後の業務フローが未整備
三つ目の壁は、適用初年度の財務諸表上の数値を正しく算定することに注力するあまり、その後の継続的な業務プロセスを軽視してしまう点です。
リース契約は、新規・更新・解約・条件変更など、日々変動し続けるものです。これらの変動をタイムリーに会計処理へ反映させる業務フローやシステム上の手当が後回しにされた結果、適用2年目以降に手作業での管理が破綻し、月次決算の遅延や数値の誤りを招くといったケースが見られました。制度対応は一過性のイベントではなく、持続可能な業務プロセスを構築することが不可欠です。
プロジェクトを円滑に進めるためのCFOの役割
では、この大きな変化にどう向き合うべきか。重要なのは、プロジェクトの目的を「導入初年度のBSを正しく作成すること」だけに置くのではなく、「基準導入後の継続的かつ効率的な業務フローを構築すること」までをゴールと定めることです。その上でCFOはプロジェクトの「オーナー」として、以下の3つの視点でリーダーシップを発揮することが求められます。
視点①:まず「インパクト分析」から着手し、全社的な課題として共有する
何よりも先に着手すべきは、自社への財務インパクトを早期に試算し、「見える化」することです。この早期のインパクト分析こそが、その後のシステム要否の判断や、プロジェクト全体の体制・方針を決定するための羅針盤となります。試算結果は速やかに経営会議等で共有し、本件が経理部門だけの問題ではなく、全社で取り組むべき経営課題であるという認識を醸成することが、CFOの最初の重要な役割です。
視点②:システム導入を「戦略的投資」として判断する
インパクト分析の結果、リース契約件数が多く、財務への影響も大きいと判明した場合、システム導入は有力な選択肢となります。その要否は、契約件数や年間の増減、手作業で対応した場合の想定工数、現在の経理リソースなどを総合的に勘案して判断すべきです。CFOはこれを単なるコストとして捉えるのではなく、将来の業務効率化、内部統制の強化、そして迅速で正確な経営判断に資する「戦略的投資」として、その投資対効果を判断する必要があります。
視点③:IFRSの知見を持つ外部専門家を有効活用する
リース期間の算定における「経済的合理性」の判断や、契約の実質を見抜く「実質リース」の判定など、新基準には会計上の高度な判断が求められる論点が多数存在します。これらの論点について、IFRSの先行事例に精通した専門家の知見を活用することは、手戻りを防ぎ、プロジェクトの品質とスピードを担保する上で極めて有効な選択肢です。
さいごに:リース新基準対応は、財務規律を見直す絶好の機会
リース新基準への対応は、一見すると手間のかかる守りの業務に映るかもしれません。しかし、その本質は、これまでオフバランスという形で貸借対照表の外にあった資産の利用実態を可視化し、事業全体の資産効率を全社的に問い直すことにあります。
CFOがこのプロジェクトを力強く主導し、データや業務フローの整備、そして必要に応じたシステムの活用を通じて効果的・効率的なオペレーション体制を構築していくこと。それは、単なる制度対応に留まらず、財務ガバナンスの強化や、非効率な資産保有・利用の見直しといった、企業経営の質を高める動きへと繋がっていくはずです。2027年に向けて、今こそCFOの戦略的リーダーシップが問われています。