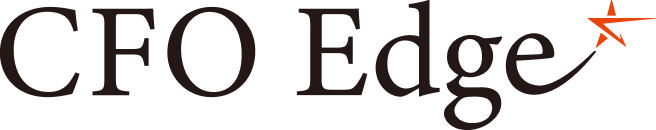はじめに
電子帳簿保存法の改正とデジタルインボイスの普及を背景に、領収書や請求書の電子化は企業のバックオフィス業務効率化の最重要課題の一つとなっています。本稿では、CFOの皆様が特に知っておくべき、電子化のメリット、潜在的なリスク、具体的な導入ステップ、そして最新の法改正や技術動向について、実践的な視点から解説します。
領収書・請求書電子化の最新動向:法改正とデジタルインボイス
電子帳簿保存法の改正:さらなる緩和と義務化の動き
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、電子取引データの保存要件が大幅に緩和されました。具体的には、税務署長の事前承認制度が廃止され、タイムスタンプ要件が緩和されるなど、企業にとって電子化のハードルが大きく下がりました。
さらに、2024年1月からは、電子取引における電子データ保存が完全義務化されました。これにより、請求書や領収書などを電子データで授受した場合、原則として書面での保存は認められなくなり、電子データでの保存が必須となりました。
デジタルインボイス(Peppol):グローバル標準の導入
デジタルインボイス(Peppol)は、請求書の作成、送付、受領を電子的に行うための国際的な標準規格です。日本でも、2023年1月からPeppolをベースとした日本版デジタルインボイス(JP PINT)の運用が開始されました。
デジタルインボイスの導入により、請求処理の自動化、コスト削減、インボイスの正確性向上などが期待できます。CFOとしては、デジタルインボイスへの対応を視野に入れ、既存システムの改修や新たなシステムの導入を検討する必要があります。
領収書・請求書電子化のメリット:CFO視点での再評価
企業が領収書・請求書の電子化を検討する背景には、働き方改革、業務効率化、コスト削減など、多岐にわたる要因が存在します。ここでは、CFOの視点から特に重要なメリットを3点に絞って解説します。
業務効率化:バックオフィス業務の劇的な改善
経費精算業務は、従業員全体が関わる間接業務の代表例です。従来の紙ベースの経費精算では、申請者は領収書を台紙に糊付けし、経理部門へ社内便で送付する必要がありました。しかし、経費精算システムの導入と領収書の電子化により、スマートフォンから経費精算が可能となり、事務作業が大幅に軽減されます。
例えば、営業担当者が外出先で領収書をスマートフォンでスキャンし、経費精算システムにアップロードすることで、帰社後の作業時間を削減できます。AI-OCR技術を活用すれば、手入力の手間を大幅に削減し、経費精算業務の効率化をさらに加速できます。
コスト削減:間接コストの大幅削減と戦略的投資への転換
紙の領収書や請求書の保管には、倉庫料や拠点間の郵送費など、見過ごせないコストが発生します。電子化により、これらの物理的な保管コストを削減できるだけでなく、税務調査や会計監査時に書類を探す時間や、郵送コストも削減できます。
さらに、電子化により生まれた余剰リソースを、より戦略的な業務にシフトすることが可能になります。例えば、財務分析や経営戦略の立案など、企業の成長に直接貢献する業務に注力することができます。
ワークスタイル変革への対応:柔軟な働き方の実現とBCP対策
労働人口の減少を背景に、フリーアドレス制やテレワークを導入する企業が増えています。領収書や請求書の電子化は、これらの柔軟な働き方を支援する取り組みの一環として重要です。
ペーパーレス化を推進することで、従業員は場所や時間にとらわれず業務を遂行できるようになり、生産性向上に繋がります。また、災害時における事業継続計画(BCP)の観点からも、電子化されたデータは安全に保管され、事業の中断リスクを軽減します。
導入のためのステップ:実践的なロードマップ
領収書・請求書の電子化を成功させるためには、以下のステップを段階的に進めることが重要です。
1. 現状分析:課題の明確化と目標設定
まず、現状の業務プロセスを詳細に分析し、課題を明確化します。例えば、経費精算にかかる時間、紙の保管コスト、監査対応の負荷などを定量的に把握します。
次に、電子化によって達成したい目標を設定します。例えば、経費精算にかかる時間を50%削減、紙の保管コストを80%削減など、具体的な数値目標を設定することで、プロジェクトの進捗を管理しやすくなります。
2. 要件定義:電子帳簿保存法とデジタルインボイスへの対応
電子化にあたっては、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。「真実性の確保」と「可視性の確保」の観点から、業務プロセス、規程、システムを見直す必要があります。
また、デジタルインボイス(JP PINT)への対応も視野に入れ、請求書の作成、送付、受領プロセスをどのようにデジタル化するか検討します。
3. 業務フローの見直し:効率化と内部統制の強化
電子帳簿保存法に対応するため、電子化の方法、承認フロー、定期検査など、従来の業務フローからの変更が必要です。
- 電子化の方法(入力方法)
書類受領後、スキャン、原本確認、タイムスタンプ付与という一連の手順が必要です。入力方法には、「特に速やか方式」(書類受領後3日以内に入力)と「業務サイクル方式」(書類受領後最大1ヶ月+1週間以内に入力)があります。AI-OCR技術を活用することで、入力作業を自動化し、人的ミスを削減できます。 - 承認フロー
改ざん防止のため、「特に速やか方式」を除き、スキャン担当者とは別の担当者が画像データと紙の証憑をチェックする必要があります。ワークフローシステムを導入することで、承認フローを効率化し、内部統制を強化できます。 - 定期検査
スキャン後、一定期間紙書類を保管し、定期検査後に廃棄可能となります。定期検査は最低年1回実施し、サンプル抽出による証憑データの整合性などを検査します。
4. システム選定:クラウドサービスの活用
- スキャナ機器
一定の法令要件を満たすスキャナ機器が必要です。複合機に加え、スマートフォンやデジタルカメラも利用可能です。 - 電子化後の保存システム
税務調査時の検索性を考慮し、国税関係帳簿との関連付け、検索機能、データ訂正・履歴保存機能などが求められます。クラウド型の文書管理システムを導入することで、初期費用を抑え、柔軟な拡張性を確保できます。JIIMA(日本文書マネジメント協会)の認証も参考にしましょう。
5. 規程の作成・変更:内部統制の整備
取引の承認、記録、資産管理に関する相互牽制体制、定期的な検査、再発防止体制などを盛り込んだ「適正事務処理規程」を作成する必要があります。
6. 従業員教育:徹底的な周知とトレーニング
新しい業務プロセスやシステムについて、従業員への教育を徹底する必要があります。定期的な研修やマニュアルの作成などを通じて、従業員の理解を深め、スムーズな移行を支援します。
7. 外部委託の検討:BPOによる効率化
スキャン、原本照合、定期検査などの定型業務は、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を検討することで、社内リソースの有効活用に繋がります。
電子化にあたっての留意点:リスク管理と継続的な改善
電子化を成功させるためには、以下の点に留意する必要があります。
- コストメリットの算出:ROIの明確化
人件費、紙の保管費、郵送費など、現状のコストを詳細に分析し、電子化による費用削減効果を明確に示す必要があります。システム導入による効率化や周辺業務の改善も考慮に入れ、全体としてのコスト削減効果を試算しましょう。 - 業務プロセスの変更:PDCAサイクルの確立
電子帳簿保存法に適合する業務フローへの変更を徹底する必要があります。新しいフローや手順が徹底されず、申請の差し戻しが多発すると、業務が非効率になる可能性があります。従業員への教育を徹底し、入力精度を向上させるなどの対策が必要です。 - セキュリティ対策:情報漏洩リスクの軽減
電子化されたデータは、情報漏洩のリスクに晒されます。アクセス権限の管理、暗号化、バックアップ体制の整備など、セキュリティ対策を徹底する必要があります。
さいごに
領収書・請求書の電子化は、業務効率化、コスト削減、ワークスタイル変革など、多くのメリットをもたらします。しかし、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があり、導入には周到な準備と計画が不可欠です。
本稿で解説したステップと留意点を参考に、最新の法改正や技術動向を踏まえ、自社にとって最適な電子化戦略を策定し、CFOとして企業の成長に貢献していきましょう。デジタルインボイスへの対応も視野に入れ、バックオフィス業務のデジタル化を推進することで、企業の競争力を高めることができます。