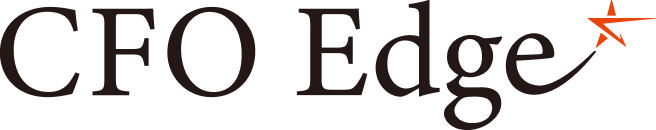はじめに
近年、世界経済の変動が激しく、企業を取り巻く経営環境はますます不確実性を増しています。原材料価格や物流コストの変動幅が大きくなり、企業業績の予測が困難な状況下において、迅速な経営判断はとても重要です。本稿では、CFO が果たすべき役割を踏まえ、そのための基盤となる決算早期化の具体的な方法について解説します。
求められる経理業務効率化と決算早期化
経営環境の不確実性の高まり
近年の世界的な経済変動により、企業は、原材料費や物流費の価格変動という大きなリスクに直面しています。外部環境の急激な変化により、企業が見込んでいた業績と実際の業績との間に大きな乖離が生じることも珍しくなく、確定した情報に基づく迅速な現状把握が不可欠となっています。
投資家が重視する情報
機関投資家は、企業の投資判断において、従来の財務情報に加え、人的資本の充実度や気候変動への対応策といった非財務情報を重視する傾向を強めています。これらの情報は、企業の将来性やリスクを評価する上で重要な要素となり、株価に大きな影響を与えるようになっています。
経理部門の課題
経理人材の不足と会計・開示制度の高度化が進む中で、経理部門には、業務の効率化と決算早期化を同時に実現することが求められています。CFO は、これらの課題を解決し、経営判断に必要な情報を迅速に提供できる体制を構築する必要があります。
決算早期化に向けた 3つの障害
多くの企業において、決算早期化を阻む要因として、以下の 3 つが挙げられます。
データの不連携・不整合
企業の成長過程で導入された複数のシステム間でデータ連携が不十分な場合、二重入力や照合作業が発生し、データの整合性確認に多くの時間と労力を要します。これは、決算業務の効率を著しく低下させ、早期化を妨げる大きな要因となります。
引き継がれた企業固有の経理ルール
過去から引き継がれている企業独自の経理ルールが、必ずしも現状に合致していない場合があります。例えば、請求書の原本がなければ費用計上ができない、わずかな会計情報の誤りも全て修正する、連結決算が確定するまで個別決算を修正し続ける、過去に監査法人から指摘された事項を絶対遵守する、といったルールは、経理処理の正確性を高める一方で、業務の効率化や決算早期化を妨げる可能性があります。CFO は、これらのルールが現在の企業の規模や状況に照らして本当に必要かどうかを積極的に見直し、必要に応じて変更する決断をしなければなりません。
進化した属人的な業務
少人数の経理部門で多くの業務を担当している場合、企業の急成長や拡大に業務の分担やローテーションが追いつかず、業務が複雑化・属人化し、業務手順が不明確になっているケースが見られます。このような状況では、特定の担当者にしか業務の内容や手順が分からず、業務のブラックボックス化を招き、決算業務の遅延やミスの原因となります。
決算早期化に向けた業務見直しのポイント
CFO は、上記の障害を解消し、決算早期化を実現するために、以下の 3つのポイントに基づいて業務を見直す必要があります。
システム化によるデータ連携
販売・購買システムと会計システムとのデータ連携や、共通マスタの導入など、基幹システムの見直しを行います。これにより、売上や仕入・経費の現場での締め処理がタイムリーかつ正確に会計に反映され、経理業務の効率化と決算早期化が実現します。
業務の棚卸しと業務プロセス改善
システム化と並行して、周辺業務の見直しも行います。システムの導入効果を最大化するためには、システム間の自動連携機能を活用しつつ、手作業による照合作業などの無駄な業務を洗い出し、削減することが重要です。また、業務ごとの目標期日を早め、早期化のボトルネックを特定し、請求書の到着遅延など、特定業務の遅延が後続業務に影響を与えていないかなど、業務プロセス全体を見直します。
計上ルールの見直し
決算早期化を阻むボトルネックを解消するために、計上ルールの見直しを行います。例えば、請求書の到着が遅れる場合、発注データや検収データに基づいて概算計上を行うことを検討します。また、経費の締め日に間に合わない請求書は翌月計上とするための金額基準を設けるなど、柔軟な対応を可能にするルールを検討します。
さいごに
CFO は、不確実性の高い時代において、迅速な経営判断と意思決定を行うために、決算早期化を重要な戦略目標として位置づける必要があります。本稿で解説した 3つの障害と、それらを解消するための 3つの改善ポイントを参考に、自社の決算業務を見直し、最適な決算早期化戦略を策定してください。