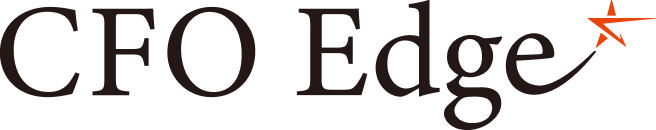はじめに
労働人口の減少、会計基準の高度化、そしてDX推進の波。経理部門を取り巻く環境は大きく変化しており、CFOはこれらの変化に的確に対応していく必要があります。その有効な手段の一つとして、経理業務のアウトソーシング(BPO)が挙げられます。本稿では、CFOの皆様が経理業務BPOを成功させるための戦略、導入ステップ、そして導入後の留意点について解説します。
経理部門を取り巻く環境変化とBPO導入の必然性
近年、経理部門は、労働人口の減少と人材不足、会計基準の高度化、DX推進、そして経営管理の高度化といった、多くの課題に直面しています。会計知識を持つ人材の確保はますます困難になり、IFRS導入や税制改正など、専門知識が必要な業務も増加しています。さらに、経理業務のデジタル化・自動化や、経営判断をサポートする高度な情報分析も求められています。
これらの課題を解決するために、経理業務BPOは有効な手段となり得ます。BPOを活用することで、リソース不足を解消し、高度な専門知識を活用し、業務効率化を図り、企業はコア業務に集中することができます。
BPO化のパターン:シェアードサービス vs アウトソーシング
経理業務をBPO化するパターンとして、大きく分けて以下の2つがあります。
1.シェアードサービス子会社への集約
グループ会社の経理業務を、特定の子会社に集約する方法です。
- メリット:グループ全体での業務効率化、コスト削減、内部統制の強化などが期待できます。
- デメリット:子会社の設立・運営コストや、グループ内での調整が必要となる点が課題となります。
2.外部アウトソーシング会社への委託
外部の専門業者に経理業務を委託する方法です。
- メリット:専門知識の活用、柔軟なリソース調整、最新テクノロジーの導入などが可能です。
- デメリット:コミュニケーションコストの発生、社内へのノウハウ蓄積が難しいといった点が懸念されます。
どちらのパターンが適しているかは、企業の規模やグループ構成、経営戦略、そして抱える課題によって異なります。それぞれのメリットとデメリットを慎重に比較検討し、自社にとって最適な選択をすることが重要です。
BPO導入のステップ:戦略的な業務の切り分け
経理業務のBPO化は、単なるコスト削減ではなく、企業の戦略的な成長を支える重要な施策となり得ます。しかし、その成功は周到な準備と計画にかかっています。ここでは、BPO導入を成功に導くための主要なステップを解説します。
① 目標・目的の決定:羅針盤を定める
BPO化の第一歩は、目的の明確化です。企業としてどのような効果を期待するのか、具体的な目標を設定し、関係者間で共有することが不可欠です。目的の不明確さは、プロジェクトの迷走を招き、期待される成果を損なう可能性があります。例えば、単に人員を代替するのか、業務改革や生産性向上を目指すのかによって、その後のプロセスは大きく変わります。明確な目標設定は、BPO対象業務の選定や運用体制の構築にも影響を与え、最終的な成果を左右します。
② 業務の棚卸:現状を把握する
目標設定後、現状の業務内容を詳細に把握します。月次・四半期決算の業務分担やスケジュールを確認し、各業務の処理件数、書類枚数、工数を可能な限り定量的に把握します。これは、外部委託時の工数見積もりに役立ち、より正確な費用対効果の算出に繋がります。業務の洗い出しは、既存の業務一覧表を活用する、担当者へのヒアリング、業務調査票を用いた記録など、様々な方法で実施可能です。正確な業務の棚卸しは、後の業務切り分けや問題点把握に不可欠であり、費用見積の基盤となるため、効率的に実施しましょう。
③ 業務の切り分け:最適な業務範囲の選定
現状把握後、BPO対象業務と自社で継続する業務を明確に区分します。切り分けの基準としては、業務の専門性と処理量が考えられます。日常業務のような処理量の多いが専門性の低い業務はBPOに適しており、決算業務のような専門性は高いが処理量の少ない業務も、標準化や見直し後にBPO化が可能です。また、属人化しやすく引継ぎが困難な業務は、業務ルールの見直しを行うことでBPO化が実現できる場合があります。
④ 自社と外部との役割分担整備:責任範囲の明確化
BPO対象業務の決定後、関係者間の役割分担を明確にします。特に、シェアードサービス子会社や外部委託会社を利用する場合、データ準備、処理、チェック、承認といった各ステップにおける責任範囲を明確に定義することが重要です。経理部門は発注者として最終責任を負うため、外部で処理された業務であっても最終承認プロセスは必須です。特に上場企業では、内部統制の観点から役割分担の設計は初期段階で慎重に行う必要があります。
⑤ 業務の見直しと標準化:効率化と品質確保
業務移管前に、現行業務の見直しを行います。非効率な業務や引継ぎ困難な業務を特定し、改善を図ることで、移管後の業務効率と品質を確保します。見直しの視点としては、業務効率化(管理資料の廃止、計上単位の見直しなど)と標準化(勘定科目・補助科目の共通化、業務マニュアル整備など)が挙げられます。特に標準化においては、業務ルールの簡素化や担当者変更時の引継ぎを容易にすることも重要です。
⑥ 業務移管・テスト運用:円滑な移行のために
移管する業務フローが決定したら、BPO先への業務移管を開始します。移管方法としては、マニュアルや手順書による説明、OJT、または両方の組み合わせが考えられます。多くの場合、マニュアルだけでは引継ぎが困難なため、テスト運用期間を設け、実務を通して引継ぎを行うことが推奨されます。テスト運用期間中は、経理担当者による詳細なチェックとフィードバックを行い、マニュアルの修正や担当者の教育を行います。マニュアルがない場合は、BPO担当者が引継ぎを受けながら簡易マニュアルを作成することも有効です。
BPO導入後の留意事項:継続的な改善と戦略的視点
経理業務のBPO化は、業務移管完了後も継続的な見直しと改善が不可欠です。安定稼働後も、予期せぬ課題や変化に柔軟に対応し、BPOの効果を最大化するための留意事項を解説します。
- PDCAサイクルによる継続的な改善
業務移管後も、シェアードサービス担当者と経理担当者は定期的な振り返りを行い、課題を共有し改善していくことが重要です。実務レベルでの誤りや運用上の課題を早期に発見し、マニュアルの更新や業務プロセスの見直しを通じて、品質向上を図りましょう。 - 社内教育体制の見直し
BPO化により、従来のOJT機会は減少する可能性があります。しかし、法律や制度の解釈、業務フローの構築、PDCAサイクルを通じた改善など、社員が経理業務や税務処理を習得できるよう、社内体制や教育方針の見直しを行う必要があります。 - 内製化のタイミングを見据える
BPO化後、業務が標準化されれば、改めて特定の業務について内製化を検討する可能性も生まれます。将来的な内製化の可能性も考慮し、ルール整備やBPO先とのコミュニケーションを継続することが重要です。 - 目標の評価と見直し
BPO化の目標達成度を定期的に評価し、必要があれば目標を修正しましょう。外部環境や社内状況の変化に対応することで、BPOの効果を最大化できます。 - BPO化後の組織体制
BPO化で生まれた時間を有効活用するため、事前に追加業務や異動計画などを検討しましょう。人材の有効活用は、BPO化の成功に不可欠です。
BPOは、経理部門の業務効率化、コスト削減、人材確保に貢献する有効な手段です。しかし、「丸投げ」するのではなく、戦略的な計画、継続的な改善、そして内製化の検討を行うことで、BPOの効果を最大化することができます。また、近年ではBPaaSに注目が集まっております。BPaaSとは、SaaSシステムを活用しながらその一部の業務プロセスを外部企業へアウトソーシングするサービスのことで、導入期間の短縮や業務の全体像を可視化したうえでのアウトソーシングを行うため、過度にBPO先に依存することを回避できるなどの利点があります。何を目的で実施するのかをしっかり把握し、自社に最適なサービスを選択しましょう。
さいごに
経理部門のBPOは、単なる業務委託ではなく、経営戦略実現に向けた一環として捉えるべきです。CFOは、BPO導入の目的を明確にし、最適な委託先を選定し、継続的な改善を推進することで、経理部門の生産性を向上させ、企業価値の向上に貢献することができます。