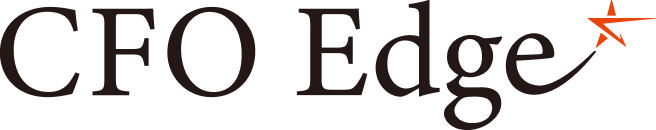はじめに
経理部門を取り巻く環境は、労働人口の減少、法規制の変更、そして経営環境の不確実性の増大により、急速に変化しています。このような状況下で、近年、経理業務のシェアード化は、単なるコスト削減や効率化の手段を超え、企業の戦略的な成長を支える重要な要素へと進化しています。テクノロジーの進化と市場の変化を背景に、経理シェアード化は新たな段階を迎え、企業に多様な価値をもたらしています。本稿では、経理業務のシェアードサービス化を軸に、CFOが主導すべき経理部門の戦略的変革について解説します。
経理シェアード化のトレンド:テクノロジーとの融合
シェアードサービスは、グループ企業の間接業務を集約し、標準化と効率化を図る手法です。従来の経理シェアード化は、業務の一部を特定の拠点に集約し、リソースの最適化を図るものが主流でした。近年のトレンドは、単なる業務集約に留まらず、デジタルインテリジェンス、クラウドネイティブテクノロジーなどを積極的に活用し、業務プロセスを抜本的に再設計することにシフトしています。
これにより、集約による効率化だけでなく、業務の自動化、高度化、そしてリアルタイムなデータ分析が可能となり、より戦略的な経理部門へと変貌を遂げることができます。特に、AIによる予測分析や自動化された経費処理などは、経理部門がより付加価値の高い業務に集中するための重要な要素となっています。
目的整理の重要性:戦略的目標と持続可能な成長
労働人口の減少と労働生産性の低迷は、日本経済における喫緊の課題です。加えて、上場企業の経理部門は、タイムリーな情報開示への要求が高まり、決算スケジュールの短縮化と業務負荷の集中に苦慮しています。このような背景から、経理業務のシェアード化は、業務効率化と標準化を通じてグループ全体の生産性を向上させ、RPAやAIなどの活用によって経理プロセス自体を革新することを主な目的としています。
しかし、シェアード化が目的と化し、業務集約のみに焦点が当たると、グループ全体の非効率化やコスト増加を招くリスクがあります。重要なのは、シェアード化を通じて何を達成したいのか、具体的な目標を明確にすることです。 例えば、コスト削減、業務効率化、データに基づく意思決定の高度化など、企業の戦略に合わせた目標設定が求められます。
経理業務シェアードサービス化の3つのパターン
シェアード化のパターンは、企業の規模、グループ構成、そして戦略によって異なります。主なパターンとしては、以下の3つが挙げられます。
本社集中型
シェアード化を通じて何を達成したいのか、具体的な目標を設定し、関係者間で共有します。
シェアードサービス子会社型
経理業務に特化した子会社を設立し、グループ全体の経理業務を集約するパターンです。専門的な人材確保やプロフィットセンター化が可能となります。ただし、本社との連携やスキル格差への対応が必要となります。
外部アウトソーシング型
外部の専門業者に経理業務を委託するパターンです。専門知識の活用やリソースの柔軟な調整が可能ですが、情報漏洩リスクやコミュニケーションコストを考慮する必要があります。
CFOは、自社の状況や戦略に合わせて最適なパターンを選択する必要があります。
経理業務をシェアード化するステップ
経理業務のシェアードサービス化を成功させるためには、以下の8つのステップを踏むことが重要です。
- 目的の整理
シェアード化を通じて何を達成したいのか、具体的な目標を設定し、関係者間で共有します。 - リソースの把握
現状の経理業務に関わる人員や組織体制を把握し、リソースの過不足を評価します。 - 現状業務の棚卸し
業務プロセス、工数、課題などを詳細に把握し、業務改善の基盤を作ります。 - 現状業務の棚卸し
シェアード化する業務と自社で継続する業務を明確に区分し、最適な業務範囲を選定します。 - 業務の見直しと標準化
業務プロセスの効率化と標準化を図り、移管後の業務品質を確保します。 - 役割分担・業務フローの決定
関係者間の役割分担と業務フローを明確に定義し、責任範囲を明確にします。特に判断を伴う領域の取り扱い・責任の所在・業務品質のチェック体制など、その後の運用を見据えた役割分担・業務フローを明確にしておくことが重要です。 - 業務移管・テスト運用
テスト運用を通じて移管プロセスを検証し、円滑な移行を目指します。 - 本番運用・PDCA
定期的な振り返りを通じて、業務プロセスを継続的に改善します。
運用上の留意点:継続的な改善とリスク管理
シェアードサービス運用においては、以下の点に留意する必要があります。
経理数値の最終責任
シェアードサービス会社に移管した場合でも、最終的な責任は本社経理や子会社経理が負います。そのため、納品物の検証方法、承認プロセス、責任範囲を明確化する必要があります。また、最終数値の確認作業については、シェアードサービス会社の品質管理体制と照らし合わせ、効果と効率性のバランスを考慮した上で、検証方法を決定する必要があります。例えば、全件照合を行うか、サンプリングによる検証を行うか、分析やチェックリストを用いた概括的なチェックを行うかなど、様々な選択肢が考えられます。重要なのは、グループ全体の効率性を考慮しつつ、過度なチェックを避けることです。
J-SOX上の論点
上場企業であれば、内部統制報告制度(J-SOX)への対応が不可欠です。シェアードサービス会社に委託した業務が、販売プロセス、購買プロセス、決算財務報告プロセスに関連する場合、シェアードサービス会社自体のチェック体制がキーコントロールとなることがあります。また、本社経理や子会社経理がシェアードサービス会社の納品物をどのようにチェックしているかも、キーコントロールとされる可能性があります。そのため、十分な事前検討とリスク評価を行い、監査法人との事前協議が必要になるケースも想定されます。
シェアード化後の人材育成
経理業務のシェアード化により、従来のOJT機会が減少する可能性があります。しかし、高度な分析業務、経営者への報告資料作成、IR業務など、新たなスキル習得の機会を提供することで、人材育成を継続できます。重要なのは、シェアード化後も社員が成長できる環境を整備し、組織全体の能力向上に繋げることです。
シェアード化対象業務の将来像:自動化と高度化
テクノロジーの進化は、経理業務の未来を大きく変えようとしています。これまで人手に頼っていた業務も、AIなどのテクノロジーの進化によって自動化される可能性が高まっています。例えば、売上計上、売掛金の消込、経費精算などの定型業務は、データ抽出から仕訳計上まで部分的にシステムで自動化されることが増えてきました。また、引当金計上や人件費計上といった決算業務も、データさえ揃えば自動化が進むと予想されます。
このような自動化の流れの中で、経理部門には新たなスキルが求められるようになります。単に業務をこなすだけでなく、自動化プロセスを構築し、運用できる人材が不可欠となるでしょう。高度に標準化されたプロセスを設計し、データ連携、エラー処理、最終チェックまでを網羅的に管理できる能力が求められます。
一方で、自動化が進むことで、より高度な経理業務へのシフトが可能になります。税効果会計、減損会計、連結決算、開示書類作成など、専門的な判断が求められる業務もシェアード化の対象となり得ます。これにより、経理部門は戦略的な意思決定に貢献する役割を担うことが期待されます。
さいごに
経理業務のシェアードサービス化とAI活用は、単なる効率化策ではありません。これらは、経理部門を企業価値創造の中核へと変革するための戦略的施策です。CFOはリーダーシップを発揮し、経営トップの理解を得ながら、全社を巻き込んだ変革を推進していくことが求められます。経理部門の戦略的変革は、企業の持続的成長と競争力強化の鍵となるのです 。